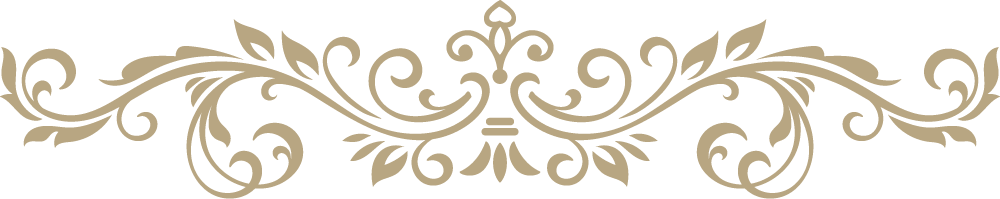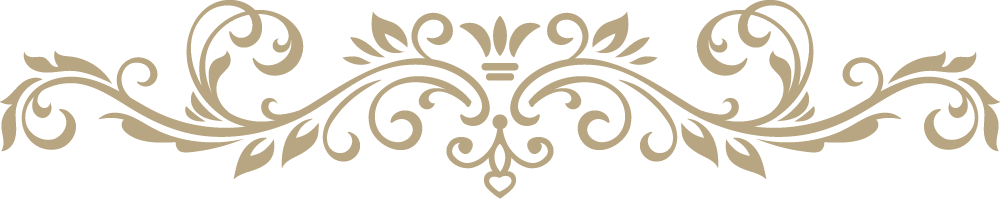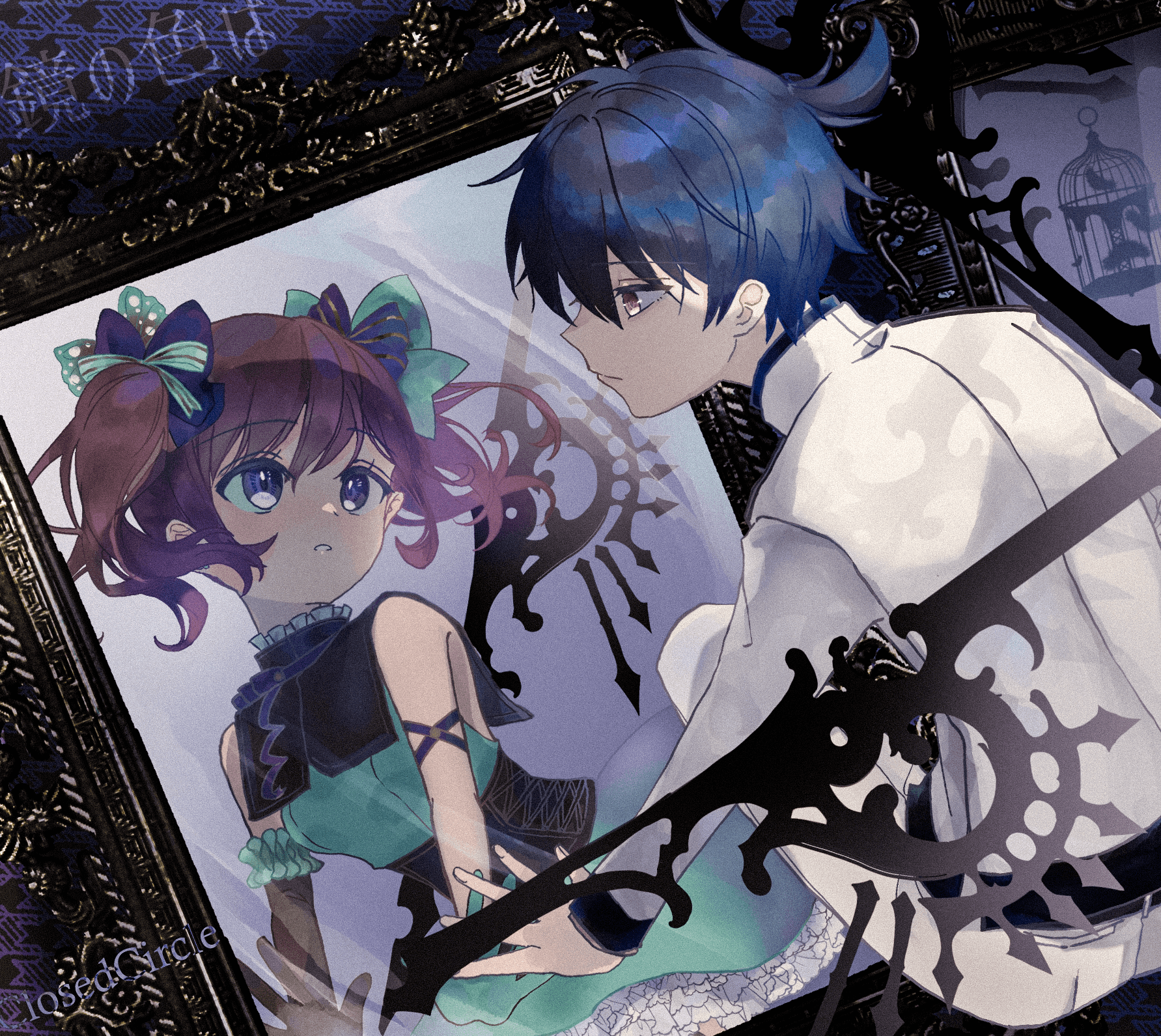しかし彼女を待っていたような、気がした。
心臓が1つ強く鳴った。
「学校で会うのは初めてだね」
彼の言う通り、バイト先ではよく顔を合わせる。ただし目当ては彼女では無くて、アイスクリーム。
――癪だ。
「二人きりなのが、初めてなんですよ?」
「そうだっけ。
で……今日はバイトは休み?」
ああ、本当に癪だ。
だから、これをつきつけてみようと、彼女は思う。
「ちょっと今日は、緊急事態なんですよね」
バチン、と彼が鞄の金具を閉じた音に、飛び上がりそうになる。
後ろめたさの仕業か。
それが転機のように、人気のない教室に危険が侵入してきた。
§2
彼女――佐伯ハイネは感じる。
先輩は何も待ってなどいない。
この時を待っていたのは、あたし、なのだ。
「あたし、昔通りすがりのプロレスラーにすくわれたことがあるんです」
「命を?」
「足下をです」
久世正宗は口を開け、そして閉じた。
「通りすがりの……」
「はい。プロレスラーに。
それから人を信じるなら、相手を選ぶようになりました」
さあ、言おう。そしてこの卑怯な恋愛劇をはじめるのだ。
言って。あたし。ほら、言って。
「助けてください、先輩」
拒絶が彼女に辿り着く方が、”先輩”の声よりも早かった。
「僕には――」
聞きたくなくて、言を遮る。
「これでも、ですか」
ハイネは相手に小型端末を突きつけた。
通話中のイラストが表示されていた。
「怪人から電話がかかってきました」
否定することも笑うこともなく、久世正宗は、
「そうか」
とだけ答えた。
§3
怪人の話をしなくてはならない。
学生の間で、噂としてまことしやかに語られている――それは突然電話を掛け、クイズを出してくる。
ルールは簡単だ。
怪人の質問に答えられなければ、あるいは間違えれば、死ぬのだ。
「誰に、電話がかかってきたんだ?」
「あたしです」
瞬間、正宗の瞳に疑惑の紅が差す。
「そうじゃないだろう?」
見抜かれている。あんなに怖かったのに高鳴る心臓は、もう恐怖のピッチで打っていない。
「あたし……の友達です」
何故彼女が追い詰められている?
状況を利用しているからだ。
「それで、なんて質問されているの?」
「鏡の色です。何色?……って」
クイズに正解したら生還――させる気はない問いかけだと、正宗は、悟られないよう嘆息した。
魔述は本来見ず知らずの相手には効果が薄いと聞く。
座標の設定が甘くなるからだ。
この問いかけの魔述は、相手にチャンスを与えることで(あるいはそう錯覚させることで)強制的に関係を結んで、最終的に死を送り込むことすら可能としているようだ。
例えば助かりたくて、命乞いをするだろう。
あるいはヒントを、聞き出そうとするだろう。
その行為自体が敵によるこちらの理解を深めさせ、座標が定まるのだ。
§4
「じゃあ放置しておこう」
「はい!? いやいや、放置って……」
「怪人の質問に答えられなければ、あるいは間違えれば、死ぬ。って話だよな。
答えの延期は、どちらにも該当しない」
ハイネは呆然と相手の顔を見上げる。
助けてくれはした? でも。あまりにも冷淡だ。
正宗は続けた。
「こっちからまだ何も返していないようだから、この魔述にはたいした効果は無いと思うけど、あくまで僕の想像だから。
【御前】に確認を――」
「待って。ください」
ハイネは友達の端末を耳に当てる。
「制限時間はあるの?」
「……佐伯さん」
ぞくりとするほど低い声で、先輩に名前を呼ばれた。
だからコール相手からの返事を、危うく聞き逃しそうになった。
返答は即時返ってくる。
「そっちから答えられない状況にしなければ、時間は無制限」
彼女は深呼吸をした。
正宗は静観している。ただ瞳の影が深い。
「解答者はあたし?」
「そう。質問を”聞いた”のはオマエだもの」
これは丁度5分前の話。
放課後、駄弁っていた友達の1人に、見慣れないIDからのコールがあった。
その子は面白そうだからとスピーカーモードにして、通話を開始した。
聞こえてきたのは、機械が軋るようなボイスチェンジャーの声。
相手が怪人と名乗ったとき、ハイネは携帯端末を取り上げ、自分の耳に当てた。
もちろんスピーカーモードを解除して。
噂を耳にしていたこと、魔述の存在を識ったばかりだったこと。
咄嗟の判断は、犠牲者が4人になる未来を回避させた。
しかし同時に。
もしも……あたしが危険に陥ったら。
先輩はあたしだけのためにいてくれる?
ずっと夢見てきた状況。
携帯端末に手を伸ばしたとき、閃光のような打算はあった。
「鏡の色は何色?」
機械が軋るように笑ったとき既に、彼女は教室を飛び出していた。
「借りるね。先に帰って」
それだけ3人の友達に言い置いて、走った。
§5
携帯端末越しの言葉の応酬は行われてしまった。
関係は結ばれた。死はこちらを照準に捉えた。
これで、通話は切れなくなった。
”そっちから答えられない状況にした”ことになる。
「そうだ! 充電……」
電池残量が黄色になっている。とりあえずケーブルに繋げば、無限に放置しておけるだろう。
ハイネはプラグを差し、何度も指し直し、手を止めた。
「先輩」
自分でも、泣き出しそうな声だと感じた。
「うん」
「充電されないです。電池、増えずに今減って――」
「どれくらい持ちそう?」
彼の声が、心持ち柔らかくなった。
彼女を落ち着かせるための、不器用な配慮。
ハイネほど彼に関心が無ければ、気付かない微細な変化だ。
「残り30分くらい――です」
数字にして、現実味を帯びた。
答えられなければ、30分後に終わる。
そしてハイネ自身は、鏡の色など見当もつかない。
「ねえ先輩」
携帯端末を保留に切り替えて、ハイネは窓際に歩み寄った。
そこで振り返ると、夕日が逆光になる。
さっきの正宗と逆だ。
彼女の表情は夕日に溶けて、一方で先輩の顔はよく見えた。
「お願いします。”僕が正解を見つける”って言ってください」
泣かずに、あるいはそれに気付かれることなく、言葉にできた。
しかし。
「僕は、嘘は言えない」
――覚悟していた。
たった30分では、彼でさえ正解に辿り着けないのだ。
彼女は食い下がる。
「嘘でも言ってください。責任を押しつけようってわけじゃないんです。
もし先輩がそう言ってくれたら」
30分間の最後まで幸せでいられる。
「あたしが勝手なことをしたツケです。だから、本当じゃなくていいんです。
僕が助けるって、言ってください」
夕日が夜を引きずって、押し寄せる。
§6
「それで佐伯さんは、鏡の色は何色だと思う?」
またはぐらかされた。
「もう……そんなことどうでもいいじゃないですか」
「どうでもよくないよ。
正解すれば助かる」
それは……その通りだけれど。
無理なのでは無かったのか。
ともあれ、助かることより、”どうでもよくない”と自分に言ってくれた気がして、ハイネは目の前が明るくなった。
「鏡の色って銀色じゃないでしょうか。銀鏡反応って習ったし」
折りたたみミラーをポケットから取り出して示す。
が、角度を変えられた。
手首に、男子の指を感じる。
彼女より強い力で傷つけてしまわぬよう、デリケートに制御された指先。
「先輩……」
こんなに近くに来られたら。
頭がぐるぐるして、余計思考が纏まらない。
「見てほしい。赤だと、言い切れないことはない」
手鏡は空を映している。
燃える天の赤。今日を死んでいく太陽の残火。
それに似た灯火を胸に灯す少年は、微かな希望を口にする。
「1つだけ思いつくとしたら、答えはこうだ。
【鏡には色がない】」
「それ、いいじゃないですか!
すごいですよ」
「……」
「色は? って聞いてこられても、ないものは答えられないですよね。
そういう引っかけなんですね」
手を合わせて飛び跳ねそうなハイネに比して、正解らしきを導いた正宗はより翳る。
§7
「まだ弱い。
こんなものに、佐伯さんの命をかけられないよ」
「それってどういう意味ですか?」
期待してもいい?
内心の声が聞こえるはずがないのに、正宗は首を横に振った。
「これは、正解のない問題なのかもしれないんだよ」
ハイネの手首に触れていた、長い指が離れる。
「鏡を借りるね」
曖昧な意識が彼女を頷かせる。
正解のない問題?
先輩の言葉を反芻する。
鏡を見なくても自分の顔色がわかった。
「なんと答えても、敵の裁量で不正解と見做せるってことですか?」
「うん。正解に辿り着きにくく、多くの可能性が考えられ、その上で誤答を誘う。
僕ならそうするだろう」
だから彼は、ハイネの懇願に、”嘘は言えない”と応じたのか。
説明の少ない先輩は、手の中でハイネのミラーをもてあそんでいる。
様々に角度を変えながら、中の色めく像を目で追う。
一方はハイネは、正解の希望が見えたところで、たたき落とされた体だ。
頬を雫がころころと落ちる。
戦略的目的以外で泣かないハイネの、嘘でない涙だった。
巻き込んでごめんなさい。
助けられないという経験をさせてごめんなさい。
言葉にできない気持ちもあるのだと、彼女は初めて知った。
頬の上、肌色をレンズのように拡大し、空中で景色を取り込んで、最後に白い制服の淡いグレーの染みになる。
涙もまた、うつろう鏡だった。
それを視界の端に捉えた正宗は行動を起こしかけ、情動を身の裡で押しとどめると同時に、一瞬鋭い視線を折りたたみミラーの表面に送った。
そして無慈悲な言葉が放たれることになった。
「僕は下校する。ここでできることは終わった」
「嘘ですよね、先輩……」
こんなところでひとりぼっち。
死に立ち会っても貰えない。
「あたし……どうすれば……」
金色のイデアの癖が移ったのか、彼は小首をかしげた。
紅い陰りを帯びた瞳には、優しさも冷酷さも存在しない。
「佐伯さんも帰っていいよ。
5分前に保留を解除してくれれば、後は自由にしてて」
呆然とするハイネを残して、先輩は早足に教室を出て行った。
§8
罰なのかと思う。
トラブルを口実に、彼に近づこうとした。
その時間を”合法的に”独り占めしようとした。
正宗自身が危険に陥ることも、その果てに傷つくことも、見て見ない振り。
そうだ。彼の反応の悪さにがっかりしていたけれど、当然だった。
巻き込んだハイネが、悪質なのだ。
彼女は、さきほどまで正宗がいた席の椅子を引いた。
倒れるように座りこむ。
噂では、犠牲者は酷い状態だったと聞く。
経緯は載っていなかったが、異常死という結果自体は、新聞にも取り上げられていた。
回答に失敗した人たち。
裏付けられる、イデアの暗躍。
何もできない自分。
どうすることが最適解だったのか。
それは今でもわからないけれど。
友達3人の代わりの、自己犠牲で終わればよかった?
これまであまりいいことがなくて、ここから挽回すると誓った。
過去の分も上乗せして、幸福になりたかった。
それなのに、状況は彼女にそれを強いるのか。
癪だけれど、それがただし方用に思えた。
どうせ残り時間で、正宗の顔を見にきてしまうけれど。
何も言わずにさよならを言って、どこか1人に慣れる場所で不正解になる。
あ、でも先輩によると、関係が構築されてないから? 座標が確実じゃないから大したことにならないはずなんだっけ。
では、この窮地は結局。欲張りで愚かな自分が選んだ、袋小路だった。
「記憶を消せないかなあ」
机の上に突っ伏すと、新しい涙が溢れた。
急いで帰宅したのは、身近な人の死なんて、見たくないからだろう。
そう彼女は推測する。
彼が今後気にしたりしないように、ハイネが助けを求めた記憶を消せたらいいのに。
タイムリミットまであとどれくらいだろう。
友達の携帯端末を目の前に掲げて、慌てた。
彼はこう言っていた。
”5分前に保留を解除して”
その時が、訪れようとしていた。
§9
「心は決まったか?」
受話器から聞こえた声は、機械が軋るようなボイスチェンジャーではなかった。
「先……輩!?」
「ああ、佐伯さん」
声は平静だった。平静なまま、何かを肉に突き立てる、嫌な音を生んだ。
吹き上がるような悲鳴。続く喘鳴。
「何してるんですか? そこはどこなんです」
「ごめん。もう時間があまりないから、先に決着といこう」
「いたいいたいいたい!!!」
苦鳴が聞こえていないように、正宗はハイネに訊ねる。
それは鏡の色の問いではない。
「好きな色を言って」
「赤です」
ハイネは即答する。
紅さの翳る瞳が好きだ。
そして、赤は、検討の中で間違いとされた答えでもある。
すすり泣きをBGMに、彼女に迷いは無かった。
先輩は過たない。
彼の返答は簡潔だった。
「わかった」
これはハイネに。
「聞こえたか? それで正解は?」
これは恐らく怪人に。
哀願する怪人に、向けられていた。
「もう……やめて」
無言。
「刺さないで深く刺さないで……死んじゃう。お願いだから……ぁ」
さんざん安全圏から殺してきたくせに、怪人は惨めに命を乞う。
「答えは君が識って……いや、決めるんだろう。
どう答えたって、難癖をつけて不正解にしてきたな」
「2本で刺すのだけはやめて……穴が繋がって脚がとれちゃう」
彼は耳を貸さない。
「それは通用しない。答えろ」
絶叫。重いものが落ちる音。
「赤は正解だな?」
思い返せば、正宗は頑なに約束しなかった。
”僕が正解を見つける”
正解を見つける気など無かったのだとハイネは思い至る。
彼がするのは、正解を認めさせること。
すなわち完璧で完全な正答だ。
「言うから、待って。お願い。痛くて」
「遅延行為をしたところで、残り時間までに殺しきるから。
そうすれば魔述が成立しないね」
「再生……しなくなちゃった……治らないよお」
「どちらがましだ? 人に考えさせた分、考えてみようか。見ろ」
鏡が割れる音。
「君の血で真っ赤じゃないか。まだ色が足りないのかな」
「正解です正解ですどうかもうやめ」
§10
ハイネは耳を端末に押し当てる。
魂が凍りそうな静寂。
危機が去ったことだけが、胸に落ちていった。
ややあって、ノイズの後に、待ちわびた声がした。
「佐伯さん、プロレスラーにすくわれた話をしていたね」
「え……えっ」
彼の行動は、何もかも唐突だ。
けれど、直前までとは違う。
慰撫の響きが不器用に混じっている。
「君の言うとおり、信じる相手は選ぶべきだった。
身近な人ほどね」
そこで通話は途絶えた。電池が尽きたのだ。
それにしても、信じるべき相手?
ハイネは思考に沈みかけながら教室に戻った。
鞄も何もかも置いてきてしまっている。
30分前おしゃべりを楽しんでいた友人は、2人だけまだ残っていた。
「待ってたの?」
「うん。○○は先に帰ったよ」
「端末返そうと思ったんだけど、明日かな」
「しゃーないねー。てか、どこ行ってたの?」
その後、端末を返す機会が佐伯ハイネに訪れることは無かった。
鏡の色について検討しながら、折りたたみミラーで背後を気にしていた正宗。
血の代わりに秘密を暴露する剣、アイ・オープナーで刺されたことで怪我を負うことはない。
しかし怪人と通じ、通話を友人たちに聞かせようとしたその生徒に、戻れる場所は無い。